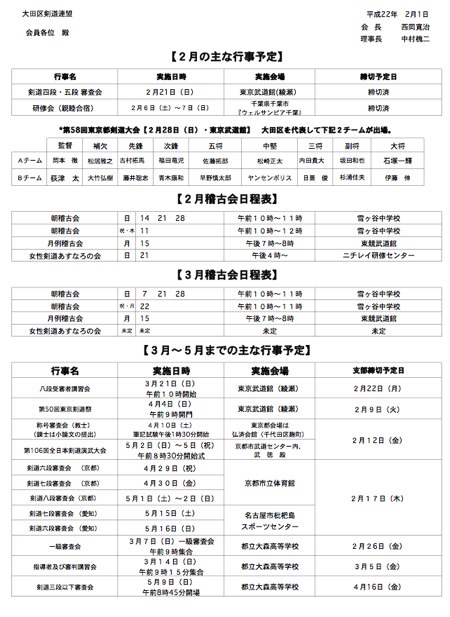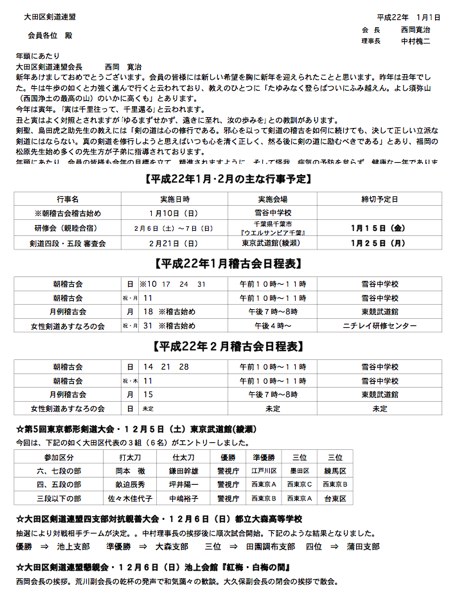■報告:平成21年度大田区剣道連盟の研修会
大田区剣道連盟副会長
田園調布支部長 大久保 康一
平成21年度大田区剣道連盟の研修会が、田園調布支部の担当で22年2月6日(土)7日(日)千葉のウェルサンピア千葉で行われました。講師を豊村東盛先生にお願いし、70名の参加者が大変寒い二日間でしたが熱心に指導を受けました。
1回目の研修は、豊村先生の恩師の一人である石原忠美先生の第8回剣道文化公演会での「沢庵と武蔵の教えを使う」の資料を利用した剣道講話が行われました。石原先生の講話は剣道原論というよりむしろ剣道哲学という内容のもので、極めて難解ですが豊村先生はそれを十分に咀嚼され、未熟な受講者にも大変判りやすく具体的かつ実践的に説明されました。竹刀の重さ40、力30、手首のスナップ30で100%、三位一体も使いすぎはダメ、極意は緩急強弱等、50歳を過ぎ、膝肩関節腰に加齢的変化が出はじめている高段者の先生方には大変役に立つ内容であったと思われます。いずれにしても三磨の位を基とし、百錬自得、冷暖自知、稽古を積み重ねる事が大切と強調されました。
寒い中での剣道講話の後は、実際に木刀を利用し、構え、姿勢(本体)、立礼、竹刀の振り方、足さばき(前進は左足で押し出し、後退は右足で押し出す)等が指導されました。この間、特に準備運動をすることなく豊村先生の巧みな指導と話術により、基本稽古をしながら自然に身体が暑くなり、防寒着を脱いでの研修となりました。豊村先生が指導された足さばき、竹刀の操作等は、先生が八段戦の試合の中で見せる、活きた足さばき、脱力した和らかい攻め合いの中で、いかなる瞬間でも打ち出せる一拍子の打突の極意を伝授されているように感じました。
短い休憩の後は木刀による剣道基本技稽古法を研修いたしました。数年前に比べると大田区の先生方は所作、動作をすでに体得されており、それをさらに高めることに時間を多く費やすようになりました。22年度からの一級審査会にこの稽古法が審査内容に取り入れられるので、いかに子供たちに指導するのかが各指導者の大きな課題となりそうです。
二時間にわたる研修の後は楽しい懇親会となりました。色々な企画があり、大変楽しいあっという間の二時間で、諸先生方、各剣友会からご寄贈いただいた30本近くあった酒も飲み干されました。二次会も大変に盛り上がり、夜遅くまで笑い声が廊下に響いておりました。
2回目の研修は7日(土)9:00から行われました。前日の指導に加え、本体を整え、脱力し、左足を動かす事なく色を見せずに繰り出す一拍子の打突が重点的に指導されました。豊村先生の一拍子の打突を竹刀で受けた先生方は、異口同音にその打突の強さと冴えに驚嘆しておりました。その後は竹刀による稽古法をさらに内容を深めた練習と、回り稽古、地稽古を行い2回目の研修を終了いたしました。研修を受けた先生方はその内容を一つでも習得され、各自の指導場所でいかに実践するかが大きな課題となります。
石原忠美先生曰く「教外別伝」道は見るべからず、聞くべからず、その見るべき、聞くべきは道の跡なり、その跡によって跡なきところを悟る。学は自得にあらざれば用をなさず。剣道という道は「道無窮」人に古今あれど道に古今なし。という事でしょうか。
お疲れさまでした!!そして田園調布支部の役員の方々ご苦労様でした。来年度は大森支部が担当ですのでよろしくお願いいたします。
大田区剣道連盟21年度研修会参加の感想
馬込剣友会 Y・S(三段)
私は初めて大田区剣道連盟の研修会に参加させていただきました。普段はあまり話す機会が少ない先生方にも御指導及び稽古をいただき、懇親会の席では剣道談議で多くの先生方と交流をもつことができました。
私にとっては剣道技術の向上と親睦を深める意味で大変有意義な二日間となりました。
今後も剣道を続けていく中で今回御指導いただいた事を少しでも実践できるよう稽古に励みたいと思います。そして来年度以降も研修会に参加させていただき、剣道を通じて多くの方々と交流を深め、研修会がより盛大になることを願っています。私のようにまだ一度も参加したことの無い方は是非来年度参加してみてはいかがでしょうか。
最後に御指導いただいた先生方、そして田園調布支部の先生方に深く御礼申し上げます
Filed under: 2)報告 by admin
Comments Off